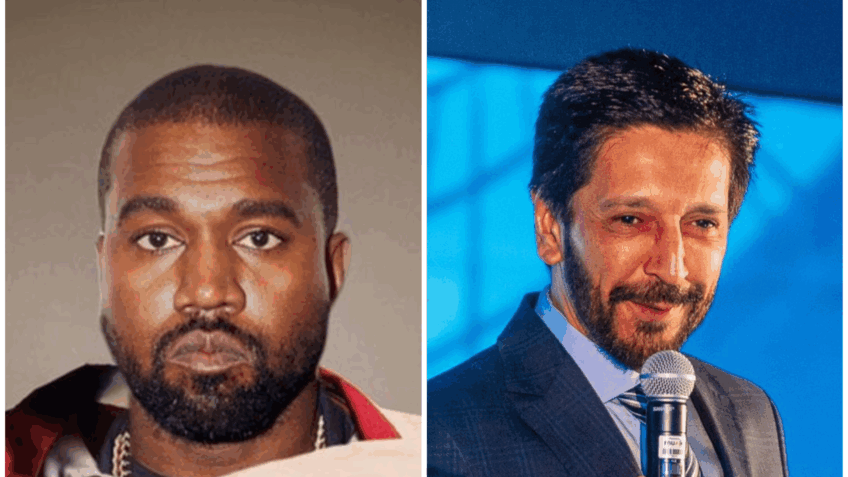地政学的な〝経済戦争〟の原型=大戦時の「特定封鎖国民リスト」=ルーズベルトとトランプの共通点《記者コラム》
1941年7月17日、米国務省は「特定封鎖国民リスト(The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals)」初版を公表した。翌1942年5月12日に改訂版も発表した。
初版は、まだアメリカが正式には第2次世界大戦に参戦していない時期(真珠湾攻撃前)に出された。そのため主な目的は、ラテンアメリカ諸国における枢軸国勢力の経済的影響力を排除することだった。リストには、ナチス・ドイツやイタリア、日本と関係があるとみなされた企業・個人の名前が挙げられ、米国企業や銀行が取引を禁じられる仕組みになっていた。
改訂版は、アメリカが参戦した後に出され、性格がより「戦時経済管理」色を強めた。つまり、単なる外交的圧力リストから、実質的な敵性資産凍結・経済制裁リストへと発展した。
1941年版では、約1800~1900件前後の個人・法人が掲載されていた。それに対し、1942年の改訂版では、その数が大幅に増加し、5千件以上に拡大した。対象は南米全域に及び、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、メキシコなどで特に多くの日本系・ドイツ系企業が追加され、一度掲載されると銀行口座が凍結され、輸入・輸出取引ができなくなった。
つまり、実質的には「銃なき戦争」、すなわち経済手段による封じ込め政策(経済戦争)であった。このリストは単なる貿易制裁ではなく、米国の経済・外交戦略の一環として位置づけられた。
軍事介入を伴わずに敵国の経済網を断ち切り、同時に南北アメリカ大陸を米国主導の経済圏として再構築する狙いがあった。経済封鎖が外交の延長として使われた先駆的事例といえる。
この「経済戦争」の構図は、80年を経た今日でも様相を変えて再現している。ドナルド・トランプ米大統領が掲げた「アメリカ・ファースト」政策の下、鉄鋼やアルミ、中国製品への高関税措置を通じて貿易相手国に圧力をかけている手法は、第2次大戦期の封鎖リストと根底で通じるものがある。いずれも軍事力ではなく経済的威圧を用い、自国の安全保障や影響圏の維持を目指す点で共通している。
1940年代のルーズベルト政権は枢軸国からの浸透を阻み、現在のトランプ政権は中国の台頭に歯止めをかけようとしている。形こそ異なるが、いずれも経済政策を地政学的競争の道具として機能させている。
10月22日付本紙《米、コロンビア支援を停止=モンロー主義2・0に南米反発》(brasilnippou.com/ja/articles/251022-41mangekyou)にある通り、トランプ政権は南米アメリカ大陸における中国の経済的浸透排除、米国の影響力回復を狙った戦略「モンロー主義2・0」を展開中だ。
この「特定封鎖国民リスト」は、経済制裁を通じた戦時外交の象徴であり、アメリカが経済的封鎖を戦略的手段として活用した初期の事例として、今も歴史的に重要な意味を持っている。改めてこのブラックリストによって日本移民が受けた被害を振り返ってみたい。

米国の「ブラックリスト政策」と中南米封鎖戦略
「特定封鎖国民の布告リスト」の第2次改訂版は、全200頁にわたる膨大なリストだ。掲載者は法律上、ドイツまたはイタリアの国民と同様の扱いを受け、資産や取引はすべて米国の行政命令第8389号(資産凍結命令)に基づき凍結された。
これはフランクリン・D・ルーズベルト大統領による布告第2497号(1941年7月17日付)を基礎とするものであり、第2次世界大戦下で枢軸国(日独伊)の経済的影響力を西半球から排除することを目的とした、米国主導の広域経済制裁政策であった。
リスト作成には、国務省、財務省、商務省、司法省、経済戦争委員会、そしてネルソン・ロックフェラーが率いた「米州相互関係調整局(OCIAA)」が関与し、いわば〝経済戦争〟の一環として遂行された。
2022年9月22日付本紙《戦争が生んだキャラ、ゼー・カリオカ=ディズニーによるプロパガンダ映画》(brasilnippou.com/ja/articles/220920-column)に詳しく書いたが、OCIAAは、第2次世界大戦直前の1940年、ルーズベルト大統領の命令により、中南米における枢軸国勢力の影響排除と、親米的世論の形成を目的に設立された。経済封鎖(ブラックリスト政策)の支援、枢軸国系企業の監視・除去、など、戦時の「情報戦」「心理戦」に相当する対外工作機関だ。後にCIAが発展させる「情報・宣伝・心理戦」の原型となった。
第2次大戦当時、米国は南米を〝裏庭〟のように扱っていた。それを明文化したものが1941年にペルーで開催された第8回汎米会議で採択された「リマ声明」だ。ここでは西半球の共同防衛が取り決められており、汎米諸国の領土や安全平和へのいかなる脅威も大陸全域の脅威と捕らえ、全加盟諸国が共同でその脅威と戦うように努めるという宣言が行われた。
中南米諸国が「ファシズム」に接近することを恐れた米国は当時、「善隣政策(Política de boa vizinhança)」を始めた。経済的優遇策と文化普及を通じて、北米の影響力を強め同盟国ブロックを形成しようとした。米国が敵と認識した相手(枢軸国)とは、南北アメリカ大陸諸国が団結して戦うという取り決めだ。同ブラックリストはその最も実務的な手段の一つであり、金融封鎖によって「敵性国系の経済的根を断つ」ことを狙ったものだった。
トランプ政権は現在は、その敵国を中国に入れ替えた形で包囲網を中南米に作ろうとしているように見える。

ブラジルにおける日系企業のリスト掲載
ブラジルは当時、南米最大の枢軸国系移民社会を抱えていた。ドイツ系、イタリア系、そして日本移民が多数を占め、特に日本人社会は1920年代以降、農業移民を基盤に都市商業へ進出しつつあった。1942年版リストには、サンパウロ市、リオデジャネイロ、サントス、ポルト・アレグレ、レシフェなどの主要都市を中心に、約250件のブラジル企業が掲載され、そのうち相当数が日系企業・団体であった。
主な日系企業を挙げると、三井物産ブラジル支店(Mitsui Bussan Kaisha Ltda.)、三菱商事ブラジル支店(Mitsubishi Shoji Kaisha Ltda.)、高島屋リミターダ(Takashimaya Ltda.)、大阪商船会社(Osaka Shosen Kaisha Ltda.)、日伯商事会社(Companhia Nippo-Brasileira de Comércio Ltda.)、南米商事(Nambei Shoji Ltda.)、大同貿易会社(Daido Boeki Kaisha Ltda.)などが代表的なところだ。
これらの企業は、日伯間の貿易を担い、日本からの輸入品(繊維・機械・工具・雑貨など)を販売するとともに、ブラジル産コーヒー・綿花・鉄鉱石などを日本へ輸出していた。
ざっとリストを見ただけでも、中小日系商店や貿易会社、例えばカーザ東山、カーザブラ拓、輪湖商会、蜂屋兄弟商会、山田商店、東山農場(Fazenda Monte D'este, Ltda.)、本田商店(Casa Honda)、岡本商会(Casa Okamoto)なども日本と資金のやり取りを行っていたことから対象とされ、「敵性資本」として扱われるようになった。
個人名としては当時の同胞社会の代表的メンバー、粟津金六、蜂屋専一、伊藤陽三、岩崎彦弥太(三菱財閥のオーナー)、海外興業株式会社、君塚慎、宮坂国人、椎野豊、辻小太郎、上塚司、山本喜誉司などの名前も散見される。

封鎖措置の実態とブラジル政府の対応
米国の初版リスト発表を受けて、ブラジル政府も1942年1月のリオ協定後、枢軸国との外交関係を断絶し、対連合国協調路線を正式に採用した。これにより、国内の独伊日系企業に対しても資産凍結などの措置が次々と取られた。特にサンパウロ州とパラナ州では、日系移民の経済活動が集中していたため、その影響は極めて深刻だった。
ブラジル政府は1942年2月11日に敵性国資産凍結令「大統領令第4166号」を出し、日本政府関連団体や日本人経営民間企業も連邦政府が送り込んだブラジル人監督官の監視下に入った。
この法令を根拠に、国民に食料を供給するコチア産業組合などの農協関係以外の日系事業体の資産が凍結された。例えば南米銀行、東山農場、東山銀行、ブラジル拓殖組合、ブラ拓製糸、海外興業株式会社、蜂谷商会、破魔商会、伊藤陽三商会、リオ横浜正銀、ブラスコット、東洋綿花、アマゾン拓殖、野村農場、旧日本病院(現サンタクルス日本病院)など、主だった日系の組織や企業が同法令を根拠に日系社会の手を離れた。繁盛していた日系商社や輸入業者は次々に閉鎖同然の状態に追い込まれ、経営者を2世や現地人名義に譲渡して生き延びる例もあった。
1942年2月、戦前から日本人街と言われていたコンデ・デ・サルゼダス街で強制立退きが執行され、5月頃から同胞社会の指導者が次々に警察に拘留された。この時、ブラジル官憲は米国の情報提供をもとに取り締まりを強化していた。日本人弾圧の最たるものがサントス強制立退き事件だ。ブラジル政府は1943年7月8日、サントス沿岸部の日本移民6500人とドイツ移民の24時間以内の強制退去を命じた。
ブラックリスト政策は、単なる経済制裁にとどまらず、移民社会の社会的地位と心理的環境に深い傷を残した。日本移民はOCIAAのプロパガンダによって「潜在的な敵」と見なされ、庶民レベルでも「Quinta-coluna(スパイ)」と呼ばれるようになっていた。

歴史的意義 ― 経済戦争としてのブラックリスト
日系社会にとってこの出来事は、経済活動の中断のみならず、「忠誠心の再定義」を迫られた歴史的転機でもあった。日本への郷愁と、ブラジル国家への帰属意識との間で揺れる中、戦後の再出発は「日本人移民」から「日系人」への意識転換を加速させた。
リストに掲載された多くの企業は、戦後ブラジル資本に吸収されたり、名称を変更して再建された。こうした再生の背後には、戦時中に培われた地元との信頼関係、そして「敵性国民」として扱われながらも地域社会に根を張り続けた移民の粘り強さがあった。
1942年のブラックリストは、単なる外交文書ではなく、国際政治と移民社会のはざまで生きた人々の運命を大きく変えた「経済戦争の記録」である。米国の政策は枢軸国の封じ込めに成功した一方で、南米各地の移民社会に分断と不信をもたらした。
戦前から始まるブラジル社会からの枢軸国民への迫害が心理的に積もり積もって、日本移民は「日本戦勝」を心の支えとする信念を強め、戦後の勝ち負け抗争の背景となった。
このブラックリストの資料は、米国在住の日系人が昨年送ってきた。彼の祖父は戦前にブラジルで貿易商として成功していたが戦中に資産凍結され、戦後、米国に再移住したという。そこで育った子孫が、昨年7月の連邦政府謝罪に関する報道が米国で行われた際、祖父の来歴に改めて注目して調べた際に発見し、本紙宛にメールで送付してくれた。
戦後ブラジルにおいて日系社会は、OCIAAのプロパガンダなど多くの困難を長い時間をかけて乗り越え、再び信頼を築き上げた。ブラックリストの苦い記憶は、経済制裁の背後にある地政学的な動きに翻弄された、日本移民史のグローバルな一断面を今に伝えている。(深)