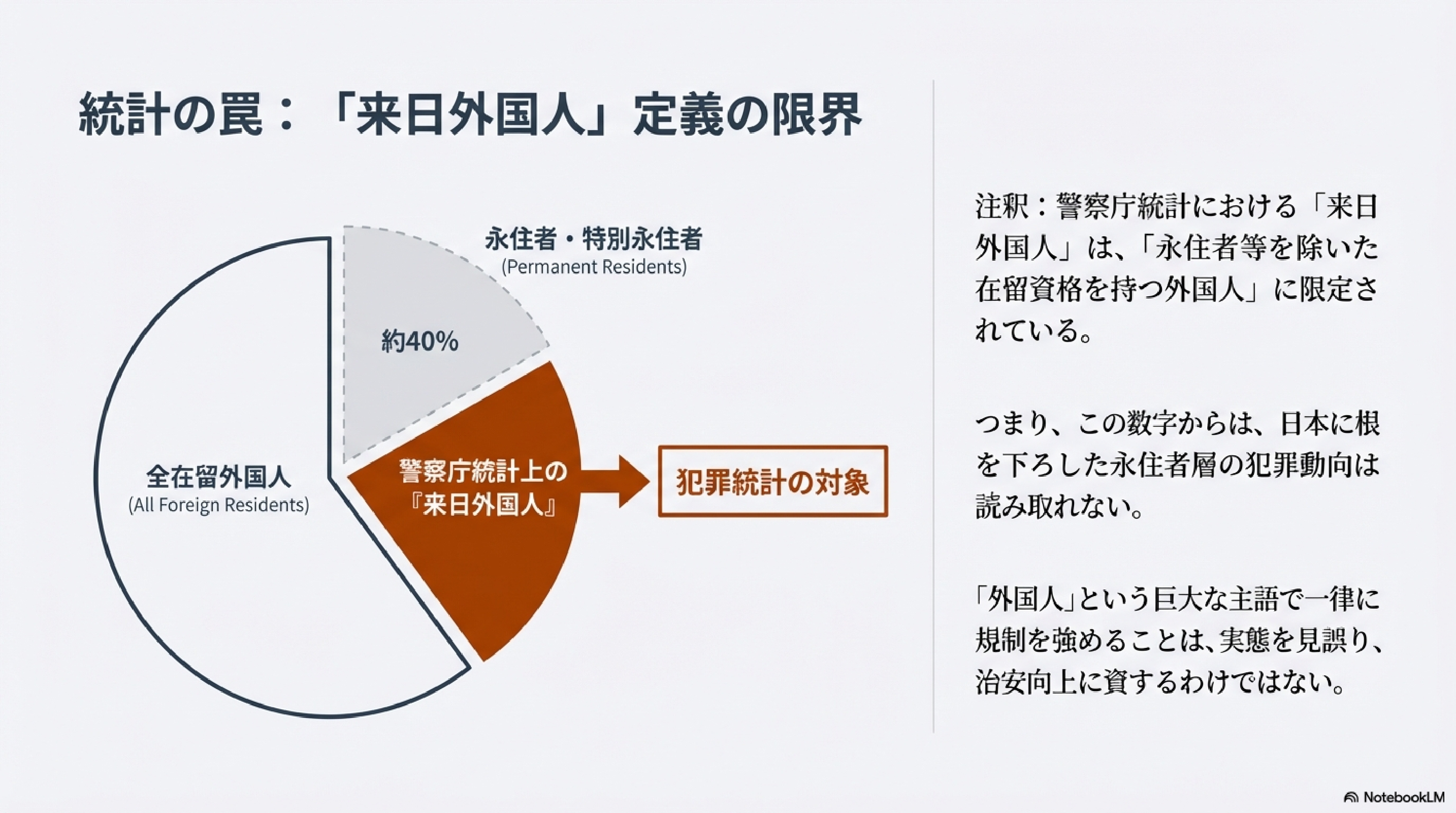日系社会を国家戦略資産に再定義を=高市早苗総理大臣への提言=対中南米外交・経済安保の視点から《記者コラム》

成田空港で足止めされる三世の青年
先日、ある日系三世から、胸に刺さる話を聞いた。
日本に生まれて公立学校に通って人格形成したのち、2009年に日本政府の帰国支援制度を利用した両親に連れられて、ブラジルへ戻った青年だ。もちろん日本語も不自由なく話す。
成人後、ビジネス目的で何度か訪日したが、そのたびに成田空港の入国審査で呼び止められ、別室に通される塩対応を受けたという。
自分が企画した訪日ツアーにも関わらず、「同行しているブラジル人の取引先は通過するのに、私だけが止められる。もしこのまま入国を拒否されたら、と強い不安を感じました」。
彼が入管職員に理由を尋ねると、「帰国支援制度を利用しましたよね」と逆に問われたという。親の判断から16年を経てなお、日本の「玄関口」で、日本に親しみを持つ人材がこうした扱いを受ける。この事実は、日本政府が日系社会との関係に長期的な視座を欠いていることを象徴しているように思える。
日本は日系人を歴史的文脈の中で「宝」と語ることはあっても、現在および将来の国益を担う主体として制度化してこなかった。その曖昧さが、現場の運用に歪みとして表出している。
この機会に地球の反対側から、高市早苗総理大臣に対し、中南米外交・経済安保の視点から、日系社会を「国家戦略資産」に再定義するよう提言したい。

2017年報告書が示した「連携」という発想
こうした状況をすでに見通していたのが、堀坂浩太郎教授らによって2017年に外務省へ提出された「中南米日系社会との連携に関する有識者懇談会」報告書(www.mofa.go.jp/mofaj/files/000254652.pdf)だ。
同報告書は、日系社会を「支援の対象」から「対等な連携主体」へと再定義し、日本外交の戦略資産として位置づけることを明確に提起した。そこでは、日系人を文化的存在にとどめず、外交・経済・人的ネットワークを支える基盤と捉える視座が示されている。
しかし、2025年の現在、この提言が国家戦略として体系的に実装されているとは言い難い。日系社会は依然として、文化交流や友好親善、単純労働力の枠内で語られ、外交、安全保障、経済安全保障といった政策領域とは切り離されたままだ。
ブラジルには約270万人、中南米全体では308万人の日系人が暮らす。これは、日本の多くの都道府県の人口規模を上回る。しかも彼らは、単なる移民集団ではなく、現地社会の中枢に浸透し、政治・経済・学術分野で一定の影響力を有している。
例えば、ブラジル陸軍だけで中将をトップに過去を含めて10人の日系将校がおり、軍全体では23人もいる。斉藤準一空軍総司令官ら大将クラスも2人おり、こんな国が他にあるだろうかと問いたい。
少なくとも歴史的には、連邦下院議員は20人以上(現在3人のみ)、日系大臣4人、中央銀行理事2人、数えきれない各省の中央官僚、累計900万部の著作売上を誇る新屋敷ロベルト(robertoshinyashiki.com.br/)ら有名著述家、山崎チヅカ映画監督、バンド「パットフー」のフェルナンダ・タカイら有名アーチストを初め、エンブラエル社副社長の横田サトシ氏ら数千の日系経営者や実業家、ジャーナリスト、法曹関係者など数えきれない人材が出ている。
この人的資源を単なる「歴史」や「感情」で扱うのではなく、日本の国家戦略としてどう位置づけるかが問われている。
いま世界は、軍事力や経済力だけで覇を競う時代ではない。言語、文化、人材、教育を通じた総合的影響力、いわゆる「見えにくい国力」が問われている。
「交流1千人」が示す政策の空白
岸田首相は昨年5月、ブラジル訪問時に「今後3年間で1千人規模の交流新プログラム」を表明した。しかし、その後の制度設計、担い手、評価指標は明確ではない。
そもそも交流は、人数目標を掲げるだけでは政策にならない。誰を、どの分野で、どの程度の期間育成し、将来どのような役割を期待するのか。そこまで踏み込んで初めて、戦略と呼べる。
これら方向性不足の原点には、日本はこれまで「海外における日本語・日本文化の普及」を国家戦略として体系化してこなかったことが挙げられる。日本食やアニメといった自発的な人気に依存する姿勢は、短期的には有効でも、地政学的競争の中では脆弱だ。
日系社会は、日本と現地社会を結ぶ人的インフラであり、「百年単位で形成された信頼資産」だ。この資産を、次世代育成、教育、研究、人材循環と結びつけ、政策として再設計する必要があるのではないか。
日本にも国際交流基金やジャパンハウスなどの取り組みはあるが、予算も限定的と言わざるをえず、尚且つ全体として断片的で、長期的な国家構想として統合されているとは言い難い。
文化の人気は移ろいやすい。しかし、言語と人材は時間をかけて根を張る。日本は今こそ、日本発の「クールジャパン」の域を超え、現地の日系社会としっかりと手を組んで、日本語と日本文化を軸にした長期的な対外戦略を構築すべきだと思う。世界にどう理解され、誰と共に歩むのか。その問いに国家として答える時期に来ている。

安倍外交が示した中南米の位置づけ
2014年8月2日、来伯した安倍晋三総理はサンパウロ市での中南米政策スピーチ(https://abeshinzo-digitalmuseum.com/pdf/20140802_SeminarSpeeches.pdf)で、「日本が近代化に向け格闘していたとき、平等な条件の条約を、日本といち早く結んでくれたのも、それから戦後、日本が国際連合に加盟する時、揃って賛成してくれたのも、中南米の国々でした。皆さん、私は思います。いまや日本が、外交の地平を広げようとするとき、中南米諸国こそは、日本が頼りとすべきパートナーであります」と明治以来の1世紀の視点から語った。
安倍総理は「地球儀を俯瞰する外交」の中で、中南米との関係をそのような長期的な視点から考えていた。
地政学の観点から見ても、南米は、もはや日本にとって「遠い地域」ではない。資源供給地として、また食料安全保障の観点からも、その重要性は年々高まっている。トランプ政権になってから米国がモンロー主義を再び掲げて影響力を取り戻そうとしている地域であり、中国が南米を重視している現実を踏まえれば、日本が人的・文化的側面から関係を補強する戦略的合理性は明白ではないか。
この文脈において、中南米の日系社会、なかでも世界最大規模を誇るブラジルの日系人社会は、日本にとって他国が容易に模倣できない戦略資産だ。270万人を超える日系人は、現地社会に深く溶け込み、日本への信頼と親近感を長年にわたって築いてきた。
冒頭の報告書も、日系人を「日本と現地社会を結ぶ懸け橋」と位置づけ、その蓄積が有形無形の国益であることを明確に指摘している。
安倍総理は、この点を直感的に捉えていた。現職総理として十年ぶりにブラジルを訪問し、アルゼンチンにも祖父の岸信介元首相以来の訪問を果たしたことは象徴的だ。安倍氏が中南米外交の指導理念として示した「共に発展し、共に主導し、共に啓発する(ジュントス)」という考え方は、同報告書にも明確に引き継がれている。
ブラジルの日系社会の存在は、この文脈において、日本が他国に対して持ち得る数少ない非対称的優位である。
そんな中南米において、日本が過去差し伸べてきた支援、ODAは累計で300億ドル以上になる。それは、「不毛の大地」と言われた広大な半砂漠地帯を「世界の穀倉地帯」に変えたセラード開発に象徴される農業協力や、輸出量で世界一になったチリのサーモン養殖に見られる技術移転に結実した。
このODAや技術協力が築いてきた信頼は、常に実績として伝え続けなければ徐々に風化する。

4世ビザを「労働政策」から切り離せ
将来を考えた際、最も重要な論点の一つが「日本で生まれ育った日系ブラジル人」、さらには「4世以降の世代」をどう位置づけるかだ。日本では「イタリアが4世以降にはパスポートの発行をやめた、米国では外国移民への取り締まりを強化などの欧米の傾向を鑑みて、日系人への特別扱いは3世まで」という論調が圧倒的だ。
だが、考えてみてほしい。ブラジル社会への浸透力・影響力という意味では、4世以降の方が価値が高いはずだ。一番価値が高い層を、あえて日本から切り離そうとしている現在の政策は、本当に日本の国益に適ったものなのだろうか。すでにいる国際人材を日本の国益にかなう方向に教育して「見えにくい国力」を飛躍的に強める。これは日本の国益ではないのか。
少なくとも日本育ちの世代は、日本語とポルトガル語、日本社会と南米社会を生活経験として理解している。これは、経済安全保障、サプライチェーン多角化、対中戦略において極めて価値の高い人的資源である。
にもかかわらず、4世ビザをめぐる議論は、いまだに労働力不足対策の延長線上にある。本来、4世ビザは「国際人材」「人的安全保障」を支える制度として、語学教育、高等教育、研究機関や企業への接続、地域定着を含めた長期的枠組みとして再設計されるべきだと思う。
地方自治体による留学生制度や研修制度も、短期的コストではなく、将来の国益への投資として位置づけ直す必要がある。
成田空港で足止めされた3世の事例は、日本が日系社会を単なる「労働力の供給源」として扱い続けるのか、それとも「国家戦略資産」として再定義するのかを問う象徴的な出来事だ。
軍事力や経済力だけではなく、人的・文化的国力の活性化をいかに制度化し、持続可能な形で活用するか。2017年の提言は、そのための出発点にすぎない。日本は今こそ、中南米日系社会を国家戦略の正面に据えるべき段階に来ている。(深)