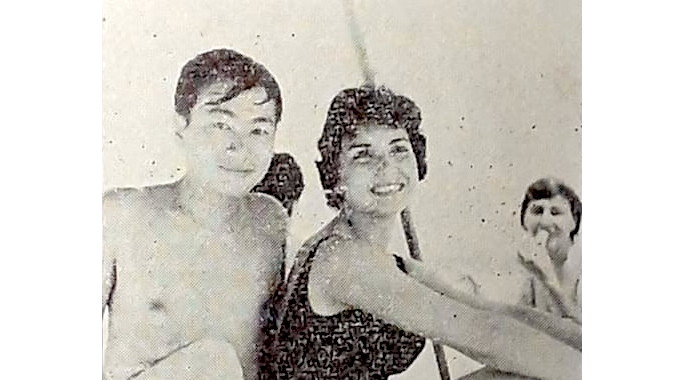寄稿=著名人たちの闘病ばなし=「僕はパーキンソンのキーパーソン!」=サンパウロ市在住 毛利律子

「僕はパーキンソンのキーパーソン!」という言葉は、「スキヤキソング・上を向いて歩こう」で世界的に有名な永六輔のことばである。難病も冗談にして笑い飛ばした永六輔さん。患者のみならず、日々、何かと悩み苦しむ一般人にも効果絶大の妙薬言葉ではないか。
永六輔は2010年、77歳でパーキンソン病と診断された。その2年ほど前からロレツが回らずラジオの話が聞き取りにくい、字が書けない、足元がおぼつかない、反応が薄い、といった異変が出ていた。そんな永さんに服薬の効果は絶大だった。言葉がはっきりし、字も書けるようになった。そして、飛び出したのがこのダジャレ!「僕はパーキンソンのキーパーソン!」には「さすが永さん、これ以上の癒し薬が他にあろうか」と感動した。
この冗談を知ったのは、やはりパーキンソン病闘病中の、恵村順一郎(えむら・じゅんいちろう・ジャーナリスト、元朝日新聞論説副主幹)の『僕はパーキンソン病』のコラムであった。恵村氏は、『報道ステーション』ではレギュラーコメンテーターとして活躍してきた。ところが、2015年春、攻勢を強める安倍政権と向き合う中で異変が襲う。重度の便秘、手足のしびれ、激烈な腰痛。下された病名は不治の病「パーキンソン病」だった。「左が利かなくなった、左翼記者」である。
他にも、多くの方々の「パーキンソン病闘病記」コラムがネット上で紹介されている。それらの闘病記から学ぶことは次のようなことであった。
人間は大自然の一部に過ぎない。ゆえに人間の身体も自然であるから、自然と同じように理解不可能なことが連続して起きる。自分の身体に起きてしまったこと。それにどう向き合うか、どのように付き合っていくか、一度は絶望の淵、地獄の底に落ちたような気持ちが、否、これは夜明け前の暗闇なのだ。
もうすぐしたら、煌々とした太陽が昇る。今このとき、病気から貴重な教訓を学んでいるのだ。闘病記が教えることは、そういう前向きな力強い勇気である。
著名人たちの闘病
この病気に罹患された有名人も多く、公表されているのは、岡本太郎、江戸川乱歩、三浦綾子、永六輔で
ある。アメリカではプロボクサーのモハメド・アリや俳優のマイケル・ジェイ・フォックス等がいる。この中から数人、名前を挙げて、この病気への理解を深めたい。
岡本太郎の場合
「老いるとは、衰えることではない。年と共にますますひらき、開ききったところでドウと倒れるのが死なんだ」これは、岡本太郎の生前の言葉だった。
岡本太郎の名が全国的に知られたのは、1970年に日本で最初に開催された万国博覧会(「日本万国博覧会」、通称「大阪万博」)でのシンボル的建造物「太陽の塔」のデザインであった。この塔は1975年に永久保存が決まり、現存している。
1990年(80歳ごろ)、パーキンソン病を発症した。そして、1996年、急性呼吸器不全により永眠した。享年84歳だった。
最晩年の岡本の症状について述べた近親者の話によると「やせ衰えていた」「身体が固まって全然しゃべらない」という。最後の展覧会でゲストとして招待されたが、作品の前で突っ立っている。最後に何か一言と促されると、うわーと大声で猛烈にしゃべりだす。しゃべり終わると、また固まっている。
岡本太郎のパーキンソン病については、国立精神・神経医療センターの長田高志医師の論文がある。その中で長田医師は、岡本のパーキンソン病発病前の柔らかい顔つきが、発病後は顔つきが非常にけわしい、硬い顔つきになっていた。この表情がパーキンソン病の特徴的な症状の一つと述べている。
その論文から、一部を要約して紹介したい。
漫画家の岡本一平、歌人で小説家・かの子との間に、1911年〈明治44年〉長男として生まれる。朝日新聞の特派員として父親の一平と共に親子で渡欧。以後約10年間をパリで過ごす。
太郎はパリ大学(ソルボンヌ大学)で哲学や民族学を学んだといわれている。ある日、たまたま立ち寄ったポール=ローザンベール画廊でパブロ・ピカソの作品を見て強い衝撃を受ける。そして「ピカソを超える」ことを目標に絵画制作に打ち込むようになる。
1942年(昭和20年)、第2次世界大戦下中国戦線へ出征。岡本は最下級の陸軍二等兵扱いだったが、高年齢である30代ということもあり、厳しい兵役生活を送ったと著書で回想している。1945年(昭和20年)、日本の降伏により太平洋戦争が終結。長安で半年ほど俘虜生活を経たのち帰国、佐世保から東京に到着するが、自宅と作品は焼失していた。
東京都世田谷区上野毛にアトリエを構え、ふたたび制作に励む。1947年(昭和22年)、岡本は新聞に「絵画の石器時代は終わった。新しい芸術は岡本太郎から始まる」という宣言を発表、当時の日本美術界に挑戦状を叩きつけた。

1976年、キリン・シーグラムのウィスキー「ロバート・ブラウン」の発売2周年企画の購買者プレゼントのために、岡本は『顔のグラス』を作成した。その時、岡本が創ったキャッチフレーズは「グラスの底に顔があっていいじゃないか・・・。顔は何時も新しい」であった。
だが、ここにも症状としてのパイドリアという幻覚症状(実態と異なった色、形が見える)が作品に影響したのではないか。晩年には病に伴う色覚異常、コントラスト感度低下が影響し、パートナーの岡本敏子のサポートを得ながら、創作活動を続けていたようだ。
「芸術は爆発だ」
パーキンソン患者は創造性が高く、これは抗パーキンソン病薬内服との関連性の有無が指摘されるが、岡本の場合は薬の治療は4年ほどだったので、創造性の高さは彼の個性そのものであったのではないかと言われる。それでも「芸術は爆破」「なんだ、これは!」と叫びながら情熱的に取り組み、世界的に知られた作品の数々は一世を風靡し、彼の個性そのものとしての芸術の爆発であった。
発症から4年という、非常に短期間で死亡しているため投薬治療は短い。死因は急性呼吸器不全による突然死が起こり得る多系統萎縮症という可能性もある、と長田医師は述べている。
俳優マイケル・ジェイ・フォックスの場合
マイケルがパーキンソン病と診断されたのは30歳の時。それから7年間、家族や限られたスタッフにしか発症を知らせないまま、俳優として活躍した。
マイケルは公表後、俳優業からいったん退き、2000年に「マイケル・ジェイ・フォックス、パーキンソン病リサーチ財団」を設立。パーキンソン病治療法の確立に向けて、寄付を募り、ロビー活動を展開するなど、元ハリウッド俳優という名前を最大限に使って、大衆の関心を呼び寄せる活動を続けている。

モハメド・アリの場合
ボクシング史上に残る数々の名勝負を戦ったプロボクサーといえばモハメド・アリといえよう。ボクサー引退3年後の1984年に42歳でパーキンソン病と診断されたが、その後も公的な場に立ち続けた。1996年のアトランタ・オリンピックで、震える体で聖火台に点火した姿は世界中のテレビの前で固唾をのんで見ていた観客に大きな勇気を与えたことは、いまだに語り継がれている。彼は、マイケル・ジェイ・フォックスの活動にも協力を惜しまなかった。
2016年、アリが74歳の生涯を閉じたとき、マイケルは次のような言葉でその死を悼んだ。「モハメドは何百万人ものパーキンソン病患者・家族のチャンピオンでした」
「私は妊娠して胎児を人工中絶し、その細胞を父親の治療のために使います」
この病気について具体的に関心を持ったのは、2000年の初めのころだったと思う。1990年後半から2000年当時、日本では医療現場で即戦力となれる人材育成のための医科大学、看護、医療福祉大学等々で、教養科目としての医学、看護英語やグローバルな医学についての基礎知識を学ぶ学科が新設されていた。
筆者もいくつかそういう科目を担当していたことから、新学期を迎えるにあたり、海外の医学教育ドキュメンタリー番組から映像を通して教材となる諸情報を収集していた。その一つ、脳神経病シリーズの中でパーキンソン病があった。
その中でも特に衝撃を受けたビデオがあった。
「父親のパーキンソン病治療のために、娘が妊娠して人工中絶した胎児の組織細胞を、父親の脳内に移植することを希望する」という内容だった。質問者に対して、その娘が嬉々として言い放った発言がコレであった。「胎児の細胞を使って父親が元に戻れるなら本望」と答えている表情がたいへん衝撃的で、深く心に残った。
3カ月までの胎児を人間とはみなさないという通念を覆したのは、1970年代のアメリカでの産科で、超音波による子宮内診断ができるようになってからである。このことは、胎児の中絶反対運動に連動していく重大な課題となるが、この件は、別の機会に紹介したいと思っている。
さてその頃は、パーキンソン病の治療法として、胎児の中脳組織を移植する研究が行われていた。これは、パーキンソン病で減少するドーパミンを産生する神経細胞を移植することで、症状の改善を目指すものであったが、倫理的な問題や、副作用として不随意運動(ジスキネジア)が出現する症例もあり、現在は、薬物療法やリハビリテーション、場合によっては脳深部刺激療法などが中心となっている。
iPS細胞を用いた移植治療は、まだ研究段階であり、臨床応用に向けて安全性と有効性の検証が進められるなど、他の最先端治療法が検討されている、ということである。(医療イノベーション推進センターCHECKNature_JUN04rev)
パーキンソン病とは
パーキンソン病は1817年にイギリスのジェームズ・パーキンソンにより初めて報告され、中年以降に発症し、筋力はあるものの、ふるえや体の動きがゆっくりとなる病気である。日本における有病率は一般的には中年以降に男女かかわらず発症し、日本では10万人に70人程度とされ、欧米の100-150人よりは少ないと言われる。神経内科の診療においては遺伝性、若年性のパーキンソン病が稀にみられる。平均発症年齢は60歳代。基本的には遺伝性ではないといわれているが、例外もあるということである。
パーキンソン病の特徴としての症状
●動作が緩慢になり、姿勢が前方に傾き、歩行が小刻みになる。動作がのろくなり、体を動かす運動量が減る症状。立ったり・歩いたりする時に、バランスを崩して転びやすい症状。
●手足の振戦、四肢が固く動きにくくなる(筋肉の緊張が高まることによるもので固縮(こしゅく)という。
●姿勢を維持する反射の障害が生じ、転びやすくなる。手首を回したり、屈伸させたりする時に抵抗を感じる症状。
●振戦はパーキンソン病の代表的な症状である。安静時にみられることが特徴で、指で丸薬を丸めるような動作に似てみえることがある。ふるえが静かにしている時におこり、物をもったり動かすと止まる。
このほか、パーキンソン病ではまばたきが減り表情が乏しくなり、仮面様顔貌と言われる硬い表情になる。話し方も小声で単調。手足の筋緊張の異常により痛みを伴うこともある。症状は左右差があるのが一般的で、たとえば左手の振るえ、動かしにくさから発症したり、歩行の際に一方の手の振りが減少する。また自律神経にも異常をきたし、便秘や頻尿、起立性低血圧などをしばしば合併する。
これらが典型的なパーキンソン病の症状だが、それ以外にすくみ足といって、なかなか歩くときの一歩目が出てこなかったり、足が床からなかなか離れない症状があったり、また先述した有名人のように、しだいに顔つきが硬くなる仮面様顔貌なども特徴的な症状である。
パーキンソン病の初期では症状に左右差があるのが一般的で、徐々に症状は両側性になって、数年から数十年かけてゆっくりと起立や歩行が困難になっていく病気なのである。
そのようなパーキンソン病患者が歴史的に初めて登場したのは1875年の『『サルペトリエール病院の写真図像集(L'Iconographie de la Salpêtrière)』の第1巻、患者の名はAnne-Marie Gavr Gavr (アンナマリー・ギャーヴ/ガヴル)であったという。
この「ふるえや動作が遅くなる病気」は、紀元前5000年のインドの文献にも記載されていて、その治療に用いられた植物の記録もあるというが、どれほど患者の心を苦しめたか、想像するだけでも辛いことである。今日のように、自由に病気について語り合い、励ましあうことのできるのは、ネット社会の恩恵の側面であることは間違いない。
【参考文献】
◎『僕はパーキンソン病 恵村順一郎の記事一覧』(https://www.asahi.com › relife › series「僕は恵村順一郎」)
◎Brain and Nerve2024 医学書院、「芸術家と神経学Ⅱ」、国立精神・神経医療研究センターの長田高志