「幽霊船」が運ぶロシア産燃料=ブラジルが経済制裁の抜け穴に
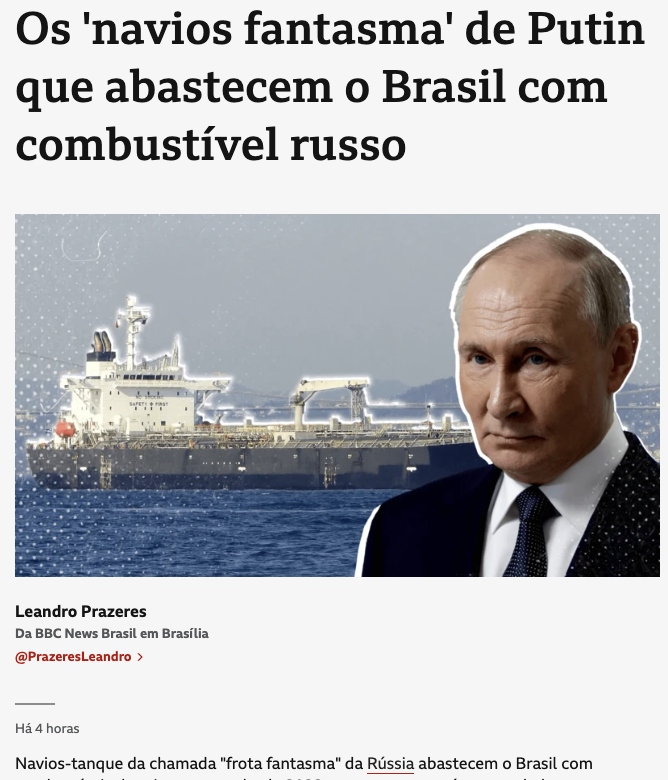
ロシアのウクライナ侵攻以降、西側諸国が対ロ経済制裁を強化する中、ブラジルがロシア産燃料の主要な輸入先として浮上している実態が明らかになった。国際社会の監視をかいくぐり、ロシアの制裁対象タンカー「幽霊船」がブラジル港湾に燃料を搬入し続けており、米国からの二次的制裁リスクがあるのみならず、制裁の実効性や地域の安全保障への懸念を浮き彫りにしていると4日付BBCブラジル(1)が報じた。
幽霊船とは、米欧専門家がロシア産燃料の輸出に用いる制裁対象のタンカー群を指す名称だ。これらの船舶は、所有者や航路を隠すために国籍を頻繁に変更したり、便宜置籍船としてタックスヘイブンに登録されるなど多様な手段を駆使している。22年8月、ディーゼル油2万6900トンを積んだ最初の幽霊船がサンパウロ州サントス港に到着して以降、制裁対象のロシア産燃料船36隻がブラジルに入港。同期間中の輸入燃料全体の約17%を占めている。
幽霊船運航は経済的、外交的、環境的リスクを伴うと、専門家は指摘する。環境面では船舶の多くが老朽化しており、保険未加入のまま航行することもあり、事故が発生した場合には損害賠償の請求は非常に困難となる。船舶は自動船舶識別装置(AIS)を意図的に停止して航行することがあり、南大西洋で一時的に「姿を消す」例も確認されている。このため、衝突や環境事故のリスクが増加する。実際、19年にブラジル沿岸で発生した原油流出事故では、原因となった船舶がAISを使用しておらず、責任の所在を特定できなかった。
外交・経済面でも懸念がある。制裁対象船を受け入れる港湾や取引企業は、米欧から制裁対象となる可能性がある。ペンシルベニア大学のベンジャミン・シュミット博士は「制裁対象船との取引は、ロシアの侵攻を間接的に支援することになる」と指摘。
米国は23年、ロシア産原油を、価格上限を超えて購入したとして、インドの海運会社2社を制裁対象に指定した。こうした前例は、ブラジルでも同様のリスクが存在することを示唆している。港湾運営会社や石油輸入業者、保険会社など、関係各所が影響を受ける可能性がある。
幽霊船の編成はG7諸国がロシア産原油の価格上限を設定し、欧州が輸入制限を実施したことに端を発する。ロシアは制裁非参加国向けに燃料を輸出するため、22年以降、500〜600隻規模のタンカー艦隊を整備した。
ブラジルではルーラ第3政権下の23年以降、幽霊船の入港が増加。サントス港とパラナ州パラナグア港が主要な受け入れ拠点となっており、ディーゼル油輸入量の60〜65%がロシア産で占められている。この結果、米国からの輸入量は縮小した。港湾当局や海軍は船舶の監視を行っているが、制裁対象船の入港阻止指示はなく、連邦警察も特別な対応を求められていない。
これらの入港は燃料供給維持や価格安定に資する一方、国際的リスクを伴う複雑な状況を示している。法的には船舶が正規書類を持ち、関係当局の承認を得て入港している限り違反は確認されていない。あくまで企業間取引という形をとっているものの、その裏には国家政策や国際関係が複雑に絡んでいる。制裁対象船との取引を続ける企業は、米欧や他国からの制裁リスクを抱え続けることになる。
船舶の運航データによれば、少なくとも6隻の制裁対象船が、23年以降もブラジルに入港している。国家水上輸送庁(Antaq)の内部資料では、幽霊船「Manta」が過去3年間で6回にわたり国籍を変更し、到着時にはAISを停止していたことが記録されている。所有企業がタックスヘイブンに所在し、後に複数の企業に所有権が移動するなど、追跡が困難な状況が確認されている。
港湾ターミナルでは船舶の入港に関して法的問題はないとされ、正規書類と関係当局の承認があれば違法性は生じない。輸送やタンク貯蔵を手掛ける物流大手のCattaliniやUltracargoなどは、国際的な制裁指針に基づく厳格な管理体制を導入し、入港船舶の監視・阻止に向けた内部手続きを整備している。










