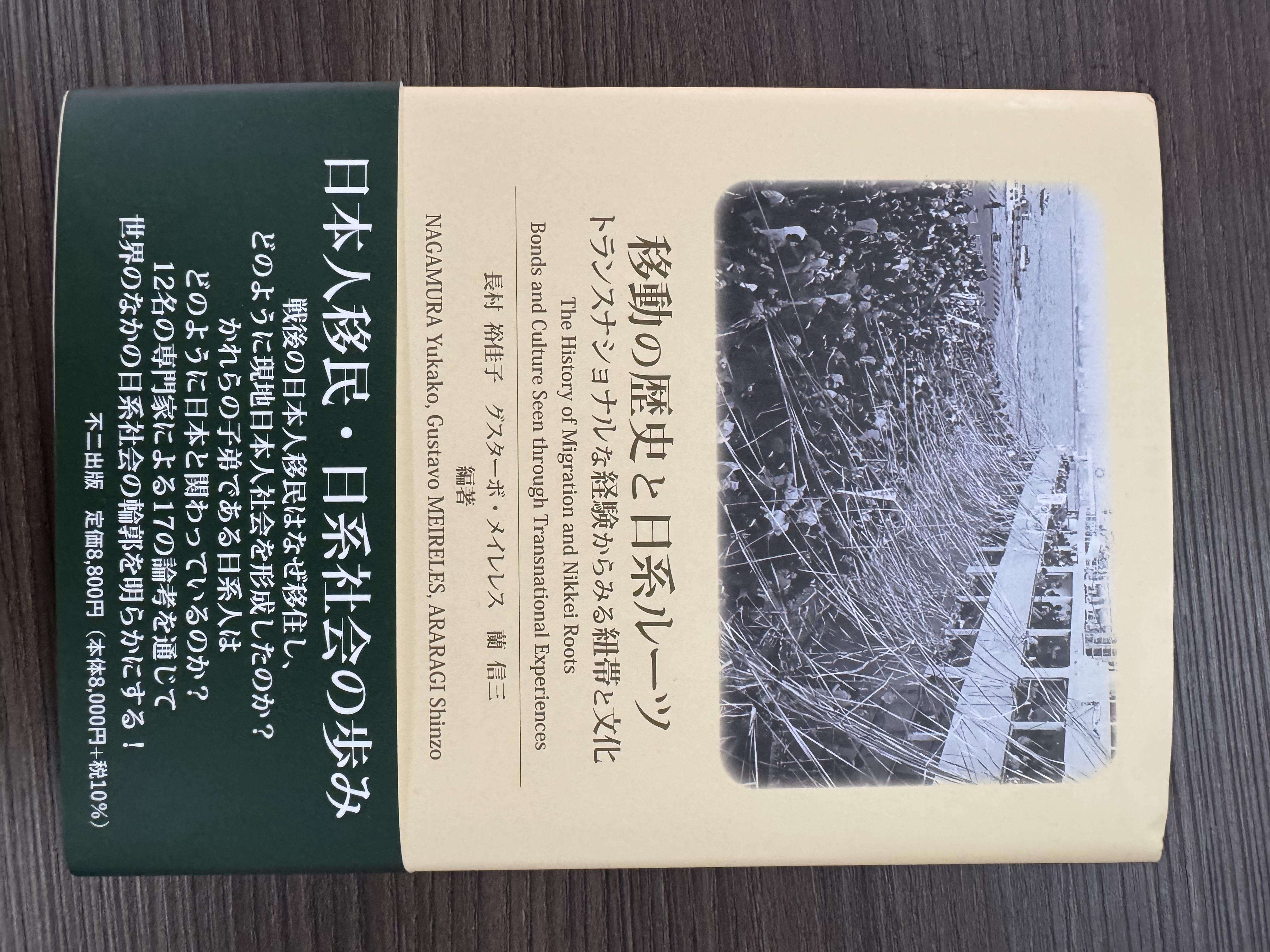書評=「外国人問題」の背後に潜む日本の闇=「共生」の覚悟問う移民魂の旅路

一世紀を超える日本移民の流転を描いた大河小説『褐色の血』がついに完結した。ブラジルの大地で汗と涙を流した一世、その開拓精神を受け継ぎながらアイデンティティの狭間で揺れる二世たち。本シリーズが丹念に紡いできた日系人の歴史は、この第3部「ヘイト列島」において、かつての母国・日本へと舞台を移し、現代社会が抱える最も鋭利な課題へと接続される。
物語は、サンパウロの貧民街に生きる子供たちのための夜間学校「テレーザ学園」設立を夢見る主人公・トニーニョと妻セシリアが、建設資金を稼ぐために「デカセギ」として訪日するところから始まる。彼らが降り立ったのは群馬県大泉町。「日本のブラジル」とも称されるこの町で、二人は日本の製造業を底辺で支える労働力として組み込まれていく。
著者の筆致は、バブル崩壊後の冷え込んだ経済状況や、リーマン・ショックによる雇用の激変を背景に、在日ブラジル人コミュニティが直面する過酷な現実を克明に活写する。長時間労働、不安定な法的地位、そして何より、言葉の壁によって教育の機会を奪われ、日本語もポルトガル語も十分に操れない「ダブルリミテッド」となっていく子供たちの悲哀。これらは決して小説の中の絵空事ではなく、現実に進行している静かなる危機でもある。
特筆すべきは、タイトルにもある「ヘイト(憎悪)」の病理への深い洞察だ。作中に登場する排外主義団体「新創会」とその代表・大迫隆司の造形は、現代日本が抱える暗部を戯画化しつつも、背筋が凍るようなリアリティを持って迫ってくる。
自らの事業失敗や社会的疎外感を、歪んだ愛国心と「外国人への憎悪」に転嫁し、ネット空間で増幅させていくその姿は、凡庸な悪がどのようにして牙をむくかをまざまざと見せつける。
「美しい国」を守るという美名の下で行われる排斥のデモ。それに対し、トニーニョたちは暴力ではなく、教育と対話という、あまりに地道で困難な道を選び取ろうとする。
かつて移民として苦難を舐め、帰国後は日系人の支援に奔走する折原健斗という人物が、トニーニョたちを支える精神的支柱として描かれる点も味わい深い。彼らの姿を通して、著者は「日本人とは何か」「国境とは何か」という根源的な問いを、読者一人ひとりに突きつけてくる。
物語の終盤、排外主義の昂揚は、ある一人の青年の暴走によって決定的な局面を迎える。その青年が抱える孤独と、自らのルーツを巡る葛藤は、多文化共生というスローガンがいかに脆く、実態を伴わないものであるかを残酷なまでに露呈させる。
しかし、著者は絶望だけを描いて筆を置くことはしない。深まる分断と衝突の果てに、トニーニョたちが何を見出し、どのような決断を下すのか。その結末は、安易な和解や感傷的なハッピーエンドを拒絶し、血の通った「共生」への覚悟を迫るものだ。それは、かつて一世たちがブラジルの荒野で見せた、生きることへの執念とも重なって見える。
本書は、単なる移民の苦労譚ではない。異質な他者との接触を通じて、日本社会の変容と可能性を問う重厚な社会派小説だ。「デカセギ」という言葉で一括りにされがちな彼らが、実はそれぞれに固有のグローバルな物語を持ち、日本人と同じように家族を愛し、未来を憂える「隣人」であることを、本書は痛切に教えてくれる。
不寛容な空気が蔓延する世界的な風潮に晒された今こそ、必読の書と言える。100年の時を超えて紡がれた魂の旅路は、ページを閉じた後も、読者の胸に熱い残り火を灯し続けるに違いない。お試しの立ち読みはサイト(www.gentosha.jp/viewer/viewer.html?cid=12690&lin=1)で。(深沢正雪)