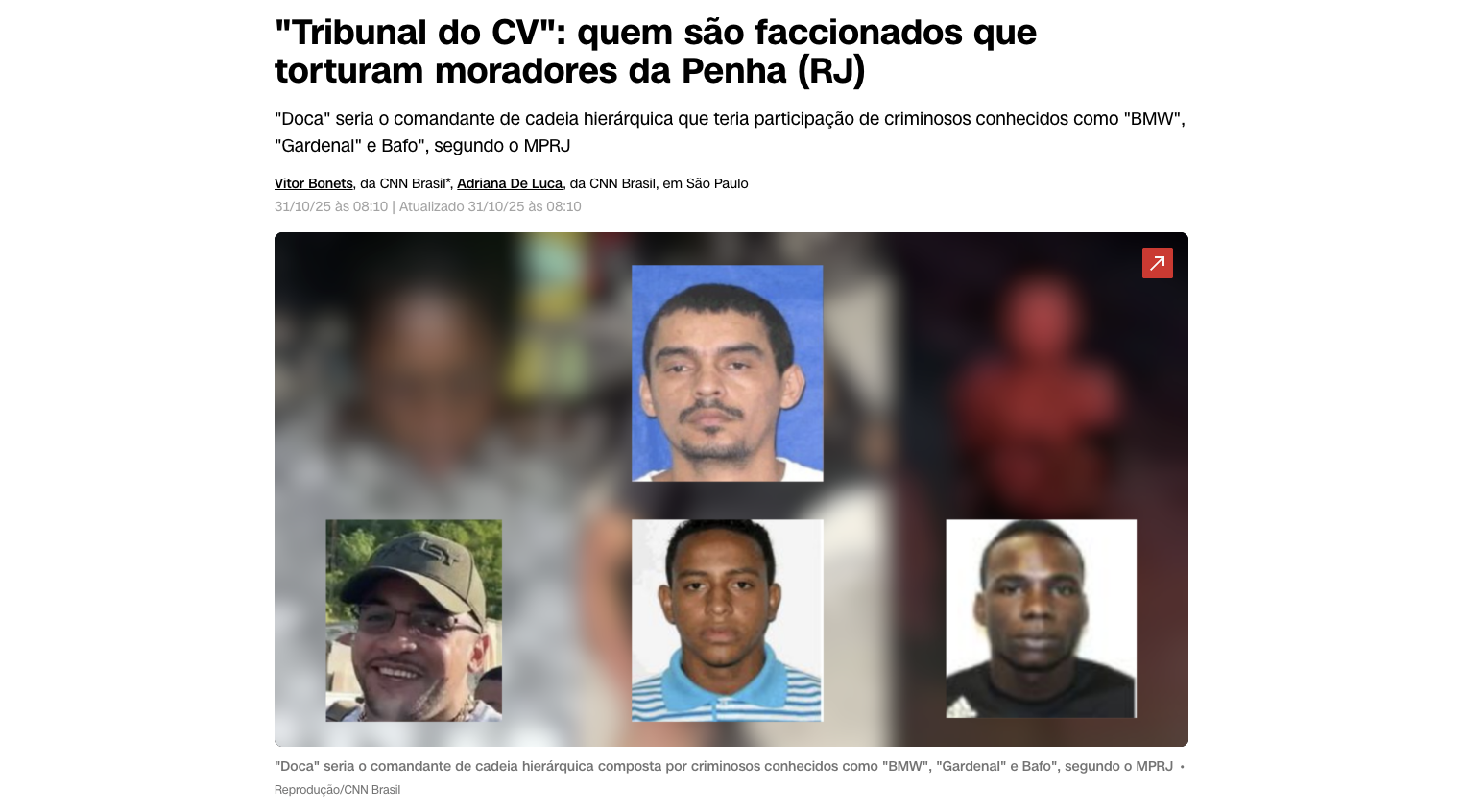ブラジル生産分布が劇的変化=農業地図が20年で大転換

ブラジルの農業地図が大きく塗り替えられつつある。サトウキビとオレンジは新たな生産拠点を開拓し、大豆は劣化した牧草地に進出。トウモロコシは中西部への集中を強めるなど、過去20年間で主要作物の生産分布が劇的に変化した。この動きは技術革新や農業境界の拡大、伝統作物を脅かす病害など、複数の要因が複雑に作用した結果だと4日付グローボ・ルラル(1)が報じた。
ブラジル農牧調査研究公社(Embrapa)が、2000〜23年の生産データをもとに実施した分析によると、サトウキビ、オレンジ、大豆、トウモロコシ、綿花といった主要作物が、それぞれ生産拠点の地理的分布を大きく変えている。調査は、各作物の国内生産量の25%を担う地域群「G25」の変遷を追跡したもので、農業における勢力地図の再編を明らかにした。
最も顕著な変化を示したのはサトウキビだ。国内生産量は2000年比でおよそ倍増し、かつてサンパウロ州内に集中していた生産の重心が、中西部を含む内陸部へと移動。2000年当時、G25はアララクアラ、ジャボチカバウ、リベイロン・プレトなどサンパウロ州6地域に限定されていた。
だが、現在はサンパウロ州プレジデンテ・プルデンテ、ミナス・ジェライス州ウベラバ、ゴイアス州南西部などが主要地に加わった。Embrapaのアナリスト、アンドレ・ファリアス氏は、「サトウキビは新規開発地への進出と、既存地域での持続的な増産の双方によって拡大。特にゴイアス州とマット・グロッソ・ド・スル州での拡張が顕著だ」と指摘する。製糖・バイオエタノール関連施設の新設も、この動きを後押しする。
一方、オレンジの生産地は州内での再配置が進む。サンパウロ州は依然としてブラジル最大の生産地であるものの、アララクアラやジャボチカバウなどの伝統的地域から、アヴァレ、バウル、ボトゥカトゥといった新興地帯へと軸足を移しつつある。
この移行の背景には、柑橘産業を脅かすカンキツグリーニング病と干ばつの影響がある。グリーニング病は世界の柑橘栽培者間で最も深刻な病害とされ、従来の果樹園を衰退させた。近年では、病害と水不足を避けるために、サンパウロ州の一部生産者がマット・グロッソ・ド・スル州など周辺州への移転を進め、ブラジルの柑橘栽培地図そのものが再編されつつある。Embrapaは「地域的縮小が進む一方で、単位面積当たりの収量増加によって全国生産量は安定している」と分析している。
大豆はブラジルの主要輸出作物として拡大を続け、その分布は分散化している。2000年時点では、マット・グロッソ州のパレシス、アルト・テレス・ピレス、バイア州バレイラス、ゴイアス州南西部の4地域で全国の1/4を占めていたが、現在はマット・グロッソ・ド・スル州ドウラドスや、マット・グロッソ州カナラナなど新たな生産地が台頭した。
大豆の拡張は劣化した牧草地の転換が主要因で、マラニョン、トカンチンス、ピアウイ、バイアの4州からなる「マトピバ」やマット・グロッソ州北部、パラー州、リオ・グランデ・ド・スル州南部に新たなフロンティアが出現。ファリアス氏は「大豆の生産集中度が下がったのは、新規開発地の急拡大による直接的な結果だ」と述べる。
これに対し、トウモロコシは逆の動きを示す。生産量自体は大幅に増加しているが、生産は中西部の限られた地域に集中している。2000年には7州13地域で全国生産の1/4を占めていたが、23年にはマット・グロッソ州アルト・テレス・ピレス、シノップ、ゴイアス州南西部、マット・グロッソ・ド・スル州ドウラドスの4地域のみで同割合を担うまでになった。背景には「サフリーニャ(2期作)」の普及がある。気候条件の制約から適地が中西部に限られ、生産が集中した形となった。
綿花の地理的集中も際立つ。23年には、マット・グロッソ州パレシス地域が国内生産の1/4を占め、同州プリマヴェーラ・ド・レステやロンドノーポリスを含めた州全体が綿花産業を支配している。Embrapaの分析によれば、綿花は主要作物のうちで最も地域的集中が進んでいる。
こうした生産地図の変化は、単に農業生産の地理を変えるだけでなく、経済・物流面にも波及する。ファリアス氏は、「主要産業を失う地域では雇用や所得に影響が出る一方、新たな生産地では倉庫や輸送網、金融サービス、技術支援といったインフラ整備が急務となる」と指摘。
同研究所のグスタヴォ・スパドッチ所長は「戦略的地域分析は、こうした構造変化を予測し、公共政策や民間投資の判断を支援するために不可欠だ」と述べ、「持続可能な農業発展のための道筋を提示することが我々の使命だ」と強調した。